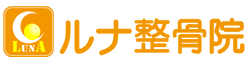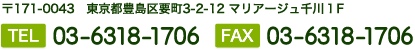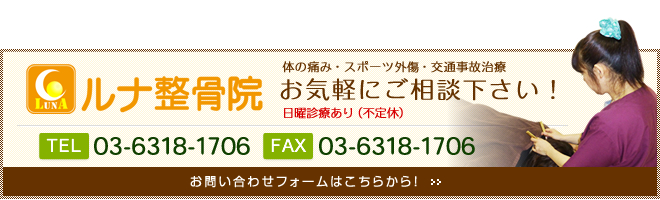手首・指の症状 ~TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)~
手首を小指側に倒したり、ドアノブを回したり、
雑巾をしぼる、キャップのふたを回すなど、
ひじが固定されている状態で、手首を回すと
手首の小指側に痛みが走る症状が多く見られます。
TFCC(三角繊維軟骨複合体)とは、
三角線維軟骨、手関節尺側側副靭帯、遠位橈尺靭帯などを含む
手首の関節の尺側支持機構の総称です。
TFCC は、尺骨と手根骨間のクッションとして働き、
手首の関節(遠位橈尺関節)の安定性を担っています。
膝の半月板と同じような構造で、
同じような働きをするとイメージするとわかりやすいかもしれませんね。
転んだ際に、手を衝いて、力が加わったり、
回内動作(肘の位置はそのままで、手首を内側にひねる動き)での作業が
過度に課せられた際に、発症しやすいといわれています。
また、「尺骨突き上げ症候群」の場合も、尺骨が三角線維軟骨を損傷して発症します。
「尺骨突き上げ症候群」とは、橈骨(肘から手首までの親指側の骨)より、
尺骨(肘から手首までの小指側の骨)のほうが長い状態のことを言います。
この状態は、先天性(生まれつき)の場合や、橈骨の骨折が元で起きる場合があります。
判断方法は、整骨院・接骨院では、圧痛があるか、「尺屈回外テスト」を行います。
が、整形外科などで精査してもらう方法もあります。
TFCCは、レントゲンでは写りません。
X線では、尺骨茎状突起(尺骨の手首付近の骨の名前)骨折の有無、
尺骨のバリアント(尺骨が橈骨より長くないかのチェック)を調べます。
確定するには、MRI検査、手関節造影検査などを行います。
MRI検査で靱帯損傷かどうかの判断をするに当たって、やはり専門的な知識が要求されます。
関節造影検査は手関節にヨード造影剤を注入して、
そこから造影剤が漏れ出さないかどうか、
漏れ出している場合は、靱帯損傷となります。
MRや関節造影よりも正確な診断が行えるのは、関節鏡です。
ただし、その検査を行うにはオペ室という無菌下で行わなければならないこと、
MRや関節造影検査に比べると患者さんへの負担が大きいことが懸念されるため、
手術と平行して行われる場合のほうが多いようです。
治療方法は、外傷性のものに対しては、3~4週間の固定を行います。
慢性的な使いすぎ、変性による場合は、
局所麻酔薬とステロイド薬の関節内注射や、付け外しが簡単な装具を装着します。
いずれも疼痛が持続する場合は、関節鏡で、TFCC中央の部分切除術を行ったり、
尺骨が橈骨に対して長いものでは、尺骨短縮術などの手術を行います。
当院では、慢性的なものに対して、レインボー療法を用いて、炎症を鎮静させたり、
JRC(関節可動回復矯正)で、肘の関節の可動、遠位橈尺骨関節の可動を正常に近づけ、
TFCCにかかる負担を軽減しながら、レインボーテープでの施術効果の維持、
テーピングによる、出来るだけ、日常生活に支障の出ない固定、
もしくは、適切な装具の選別を行います。
状態を診させていただき、整形外科へのご案内もさせていただきますので、
ご相談ください。
お役に立てたら、右下の
ぽっちっと・・・お願いします